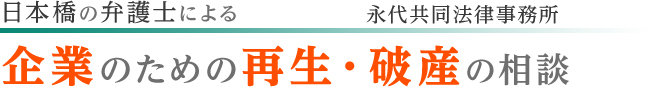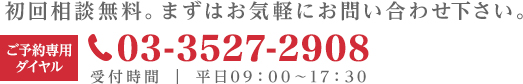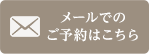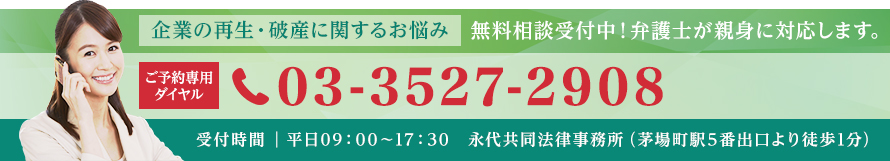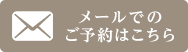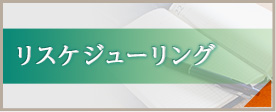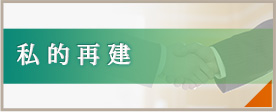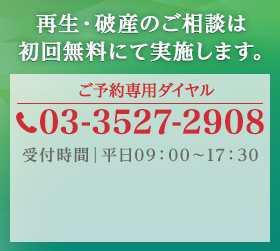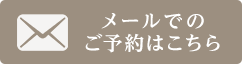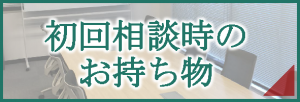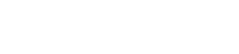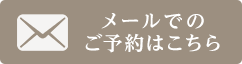新型コロナウイルスの影響により、倒産可能性がある企業がとるべき対応
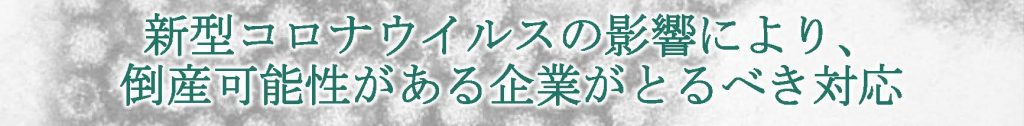
公開日:2020.6.11
1 資金繰りが悪化した企業が取れる策
①政府支援策の検討
もともと用意されていた制度でも、特例的に要件が緩和されたり、事後の届出が許されたり、支給率が増額されたりといった救済が用意されているものもあります。これらを検討し、倒産を回避できる場合があります。
代表的な政府支援策の例(概要)は、次のとおりです(詳細の要件は、個別に検討する必要がございます。制度や上限金額等も随時変更がありますので注意を要します)。
└雇用調整助成金
:新型コロナウイルス感染症の影響により1か月の売上が5%以上低下した会社に対して、休業手当の最大9/10を支給する助成金(8330円/1日上限。*上限緩和に向け、制度変更中)
└持続化給付金
:新型コロナウイルス感染症の影響により1か月の売上が50%以上低下した会社に対して、最大200万円を給付する助成金
└感染拡大防止協力金
:「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請に対応した会社に、50万円(2店舗以上ある場合には100万円)が支給される制度
└新型コロナウイルス感染症特別貸付
:日本政策金融公庫が管轄し、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が5%<以上低下した会社に、一般枠と別枠で最大6000万円まで融資をおこなう制度
└セーフティネット保証4号・5号
:中小企業庁が管轄し、新型コロナウイルス感染症の影響が生じている幅広い業種につき、一般枠と別枠で借入債務を保証する制度
└雇用調整助成金(厚生労働省)
└持続化給付金(経済産業省)
└感染拡大防止協力金(東京都)
└新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
└セーフティネット保証制度(中小企業庁)
②キャッシュフローの改善
追加融資などの社外のサポートも大切ですが、これと同時に急速な資金繰りの悪化を社内の対策によって食い止める努力をすることもとても重要です。
特に、急速な資金繰りの悪化はキャッシュフローの悪化という数字で現れてきます。
そこで、以下ではキャッシュフローを改善するために採りうる手段をご紹介します。
└債権回収を厳格に管理
:資金繰りが悪化する前の平時の経営状況であれば、債権回収が不十分であってもキャッシュフローに大きな影響を及ぼさないため、債権回収が十分に行われていないケースが多く見受けられます。
債権回収が不十分なケースにおいては、現実的に回収可能性が乏しい取引先もありますが、実際には請求や催告が適切ではないこともあります。
急速に資金繰りが悪化する状況でキャッシュフローを改善するためには、迅速に債権回収を行うことが大切といえます。
その際、取引先の対応次第では、弁護士に依頼して、内容証明郵便を送付するなどして、積極的に債権回収を進めていくことも検討すべきでしょう。以下のような手段がございます。
| 1 支払約束 | 支払約束書・念書 | 請求書等 |
| ★債務弁済公正証書 | 請求書・契約書等 | |
| 2-1連帯保証 | ★連帯保証人・公正証書 | |
| 2-2 担保物 | ①不動産 | 登記簿謄本 |
| ≒強制執行(仮差押)における差押(仮差押)対象 | ②動産・集合動産・在庫・現金 | 物件明細・所在 |
| ③預貯金 *一部全店照会有 | 金融機関+支店名 | |
| ④売掛金・集合債権・賃料債権 | 会社名+所在地 | |
| ⑤株式/会員権/保険 | 会社名 | |
| ⑥自動車・船舶等 | 車検証等/ナンバー | |
| ⑦給与・役員報酬等 | 会社名 | |
| 3 法的手段 | ①弁護士名 内容証明その他 | |
| ②訴訟・支払督促・調停 | *期間・コスト | |
| ③仮差押・仮処分 | *要担保金供託 | |
| 請求の20%程度 | ||
| ④強制執行 | *要債務名義 |
└支払いサイクルを伸ばす(リスケジュール)
:キャッシュフローを改善するためには、売掛金の回収サイクルを短縮することも大切ですが、現実的には、取引先とのパワーバランスや関係性などによって、売掛金の回収サイクルを短縮することは困難な場合がほとんどです。
そこで、同じ効果が望める現実的な方法として、支払いサイクルを長くすることが挙げられます。
例えば、取引先の支払いをなるべく後払いすることや、クレジット、済などが可能であればこのような決済を利用することなどが考えられます。
特に金融機関oの借り入れは、キャッシュフローの重要部分を占めるケースが多いので、元金の縮小、借り換え、元本据え置き(利払いのみ)等の方法で、劇的に負担が軽くなることもあります。
③ビジネスモデルの転換
新型コロナウイルス禍は、いわば外部要因による「天災」であり、強制的に、人の生き方、働き方の大幅な変容を迫っています。
ビジネスモデルを模索するうえでは、いわゆる「5つのJ」が参考になります(情報、実務経験、時間、人脈、情熱)。
上下の展開、左右の展開などがしやすいです(例 レストランにおけるテイクアウト開始など)。(なお、新規の業種・業態に挑戦するときは、適法性のチェックを忘れずおこなってください)
これまでにもあった業種・業態へのシフトチェンジでは生き残れなくても、まったく新しいビジネスモデルを生み出す可能性もあります。
事業を再構成して、縮小してでも再出発することも考えなければならないかもしれません。
2 それでも倒産・破産してしまう場合の流れ
上記のような、あらゆる対策を講じても、資金繰りの悪化を食い止めることができない場合も当然に想定されます。
そうした場合、債務者企業は、資金繰りが破綻する前に、債務整理の手続を取る必要があります。
債務整理の手続には私的再生と法的再生の2種類があります。
└私的再生
私的再生のうち、根拠法令に基づき制度化された手続のことを「準則型私的整理手続」といい、主に中小企業再生支援協議会や特定調停を用いた再生支援手続などがこれにあたります。
私的再生は、原則として金融機関のみを債務整理の相手方とするため、法的整理のように裁判所に申立てをしたことを原則として表に出さずに、債務整理を進めることができます。これにより、取引先を債務整理に巻き込まず、また、事業への信用不安を回避できる、というメリットがあります。
私的再生の各手続の詳細には触れませんが、大まかにいうと、事業再生ADRは大企業が利用することが多い手続であり、中小企業再生支援協議会による再生支援手続は中小企業のみが利用できる手続です(医療法人などは不可)。
これらの手続に共通する特色としては、対象債権者の「全員の同意」により事業再生計画を成立させる必要があるということです。一行でも反対があると計画が成立しないという点で、ハードルは高いともいえますが、主要金融機関の支援がある場合や債権者が少ないケースなどは比較的スムーズに手続が進むこともあります。
└法的再生(民事再生、会社更生)
法的再生は裁判所の監督下で事業の継続を図りながら事業を再建する手続であり、民事再生と会社更生があります。
民事再生は債務者自身(現在の経営陣)が裁判所の監督下で引き続き経営を行うDIP(debtor in possession)型が原則であり中小企業向けの手続と言われ、会社更生は裁判所が第三者の弁護士を管財人に選任しその管財人が経営を行って事業再建にあたる手続(管理型)が原則であり大企業向けの手続と言われます。もっとも、古くはそごう、最近ではタカタのように大企業が民事再生を利用する事例はあります。また、リーマンショック直後の2009年1月から東京地裁でDIP型の会社更生の運用が導入され、その後、大阪地裁などでも採用されています。こうしたことから「民事再生=中小企業」「会社更生=管理型」という図式は必ずしも当てはまらなくなってきています。
民事再生・会社更生では、金融機関のみならず、商取引先も対象として手続を進めるのが原則となり、また、裁判所や裁判所の選任する監督委員等への報告や一定の行為をする場合の許可手続等も必要になります。他方で、法的再生の場合には、多数決原理が働きますので、私的再生とは異なり一部債権者が反対したとしても、再生計画案を成立させることが可能です。
バブル崩壊後に施行された民事再生法、リーマンショック後のDIP型会社更生の導入など、法的再生は大きな経済危機のたびに債務者のニーズに即した手続のあり方を模索してきたといえますので、今回も大きな経済危機となれば新たな運用などを模索する動きが出てくるかもしれません。
└法的清算(破産)
これらでも抜本的解決が難しい場合は、破産処理にて切り抜けることとなります。
3 弁護士に依頼する場合の費用
弁護士に依頼する場合の費用はこちらの弁護士費用ページをご覧ください。
4 代表者の破産
5 実績のある弁護士に依頼すべき理由
弁護士は慎重に選ぶ必要があります。重視すべきものに「実績」があります。
自己破産に関する知識や対応スピードに関わってきます。
専門外の弁護士であっても、画一的なルールに従えば自己破産を取り扱うことが可能です。ところが、破産を望む人の状況はケースごとにまったく異なります。裁判所に返済義務の免除を認めてもらうため特別対応を必要とする人もいれば、破産手続きそのものを考え直したほうがよい人もいます。リスタートのために、取引先や従業員等との間できちんと取り決めをしておくべきことも少なくありません。
実績のある弁護士であれば、こうした「1人1人の状況に合った対応」を柔軟に提案することが出来ます。
ご相談にリスクはありません。
実績ある当事務所にぜひお気軽にご相談ください。
ご注意
■本記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
また、本記事は、医療情報を提供するものではなく、新型コロナウイルスに関する医学的な側面の知識を提供するものではありません。
■当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
■本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。